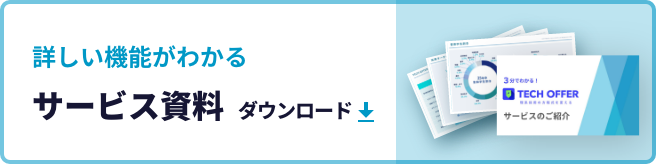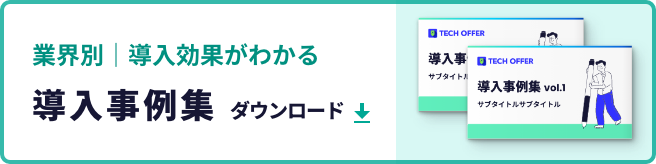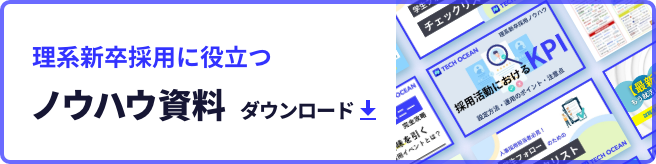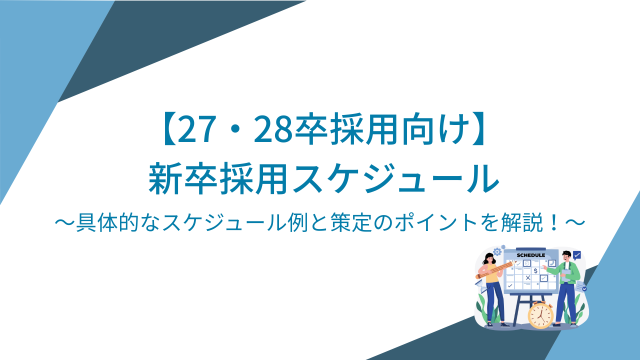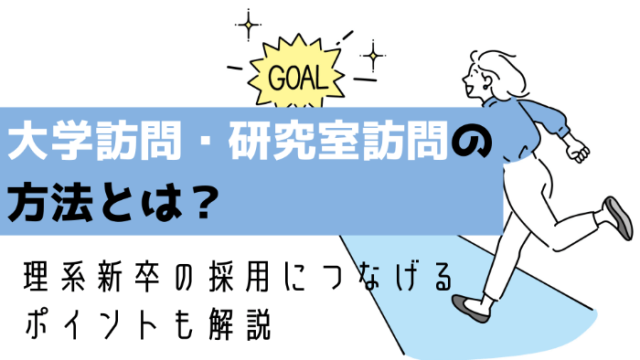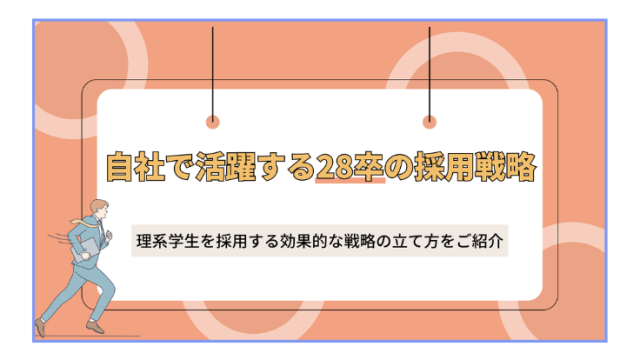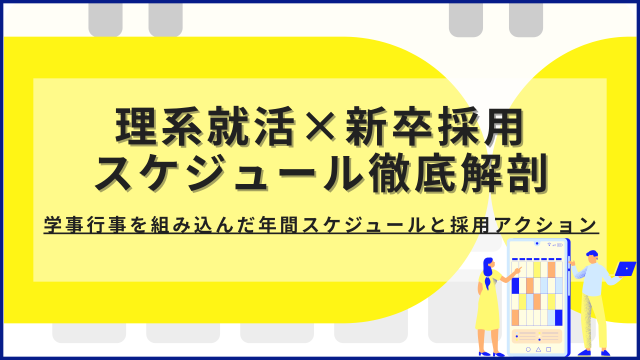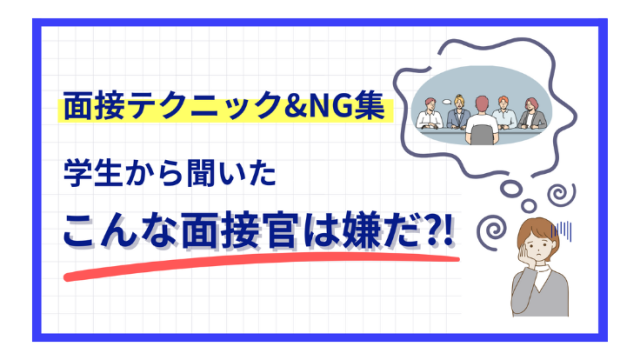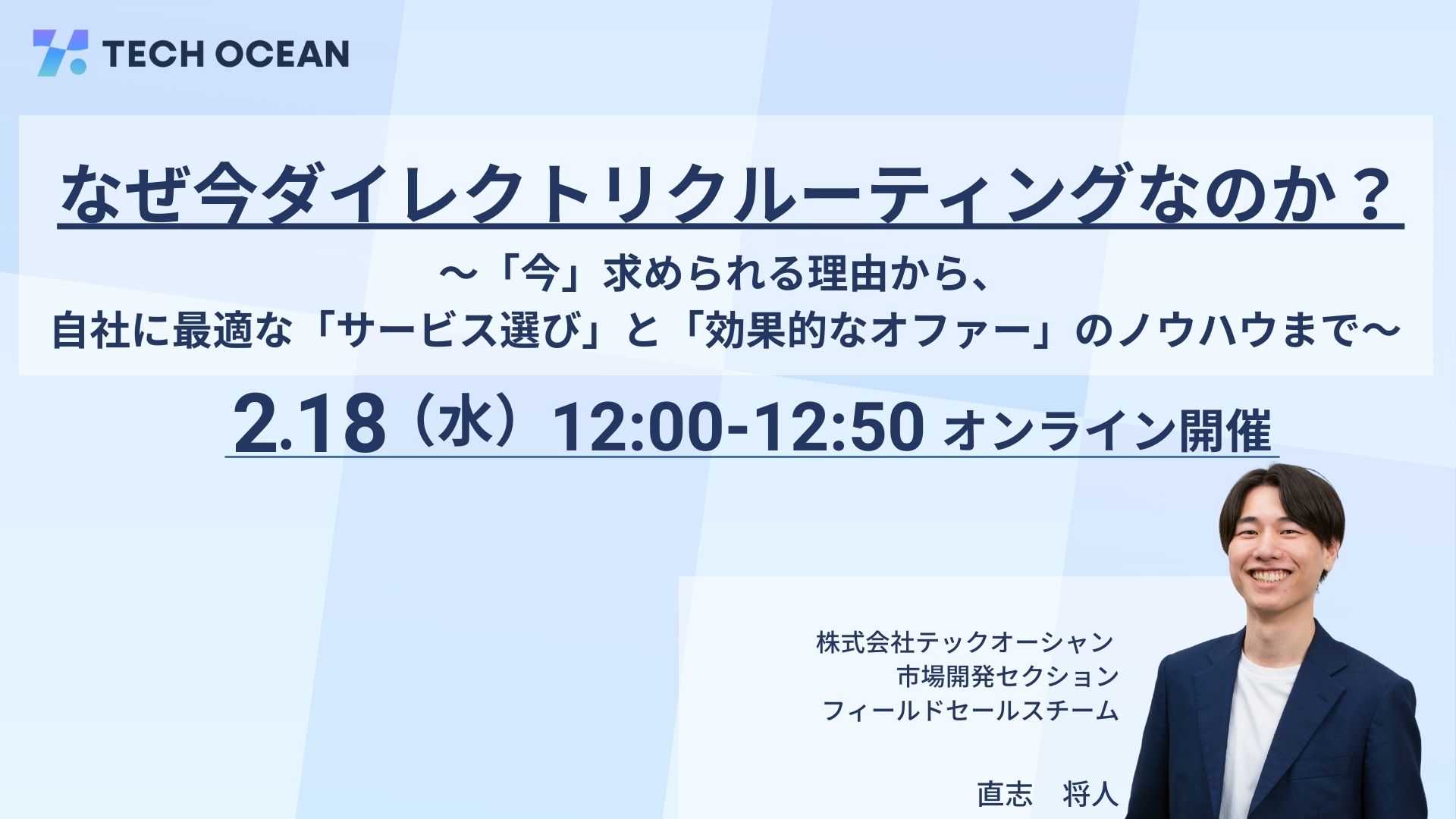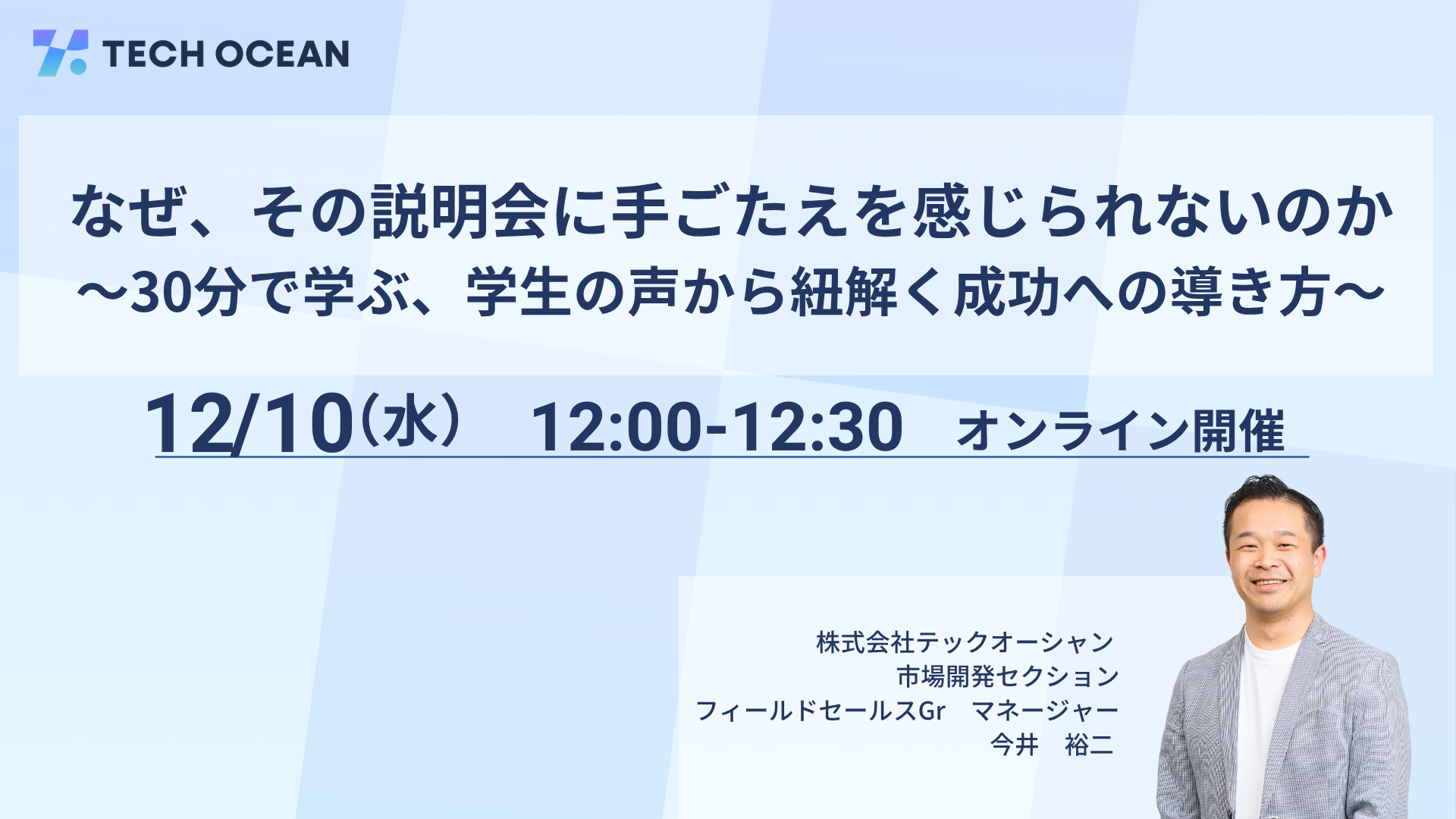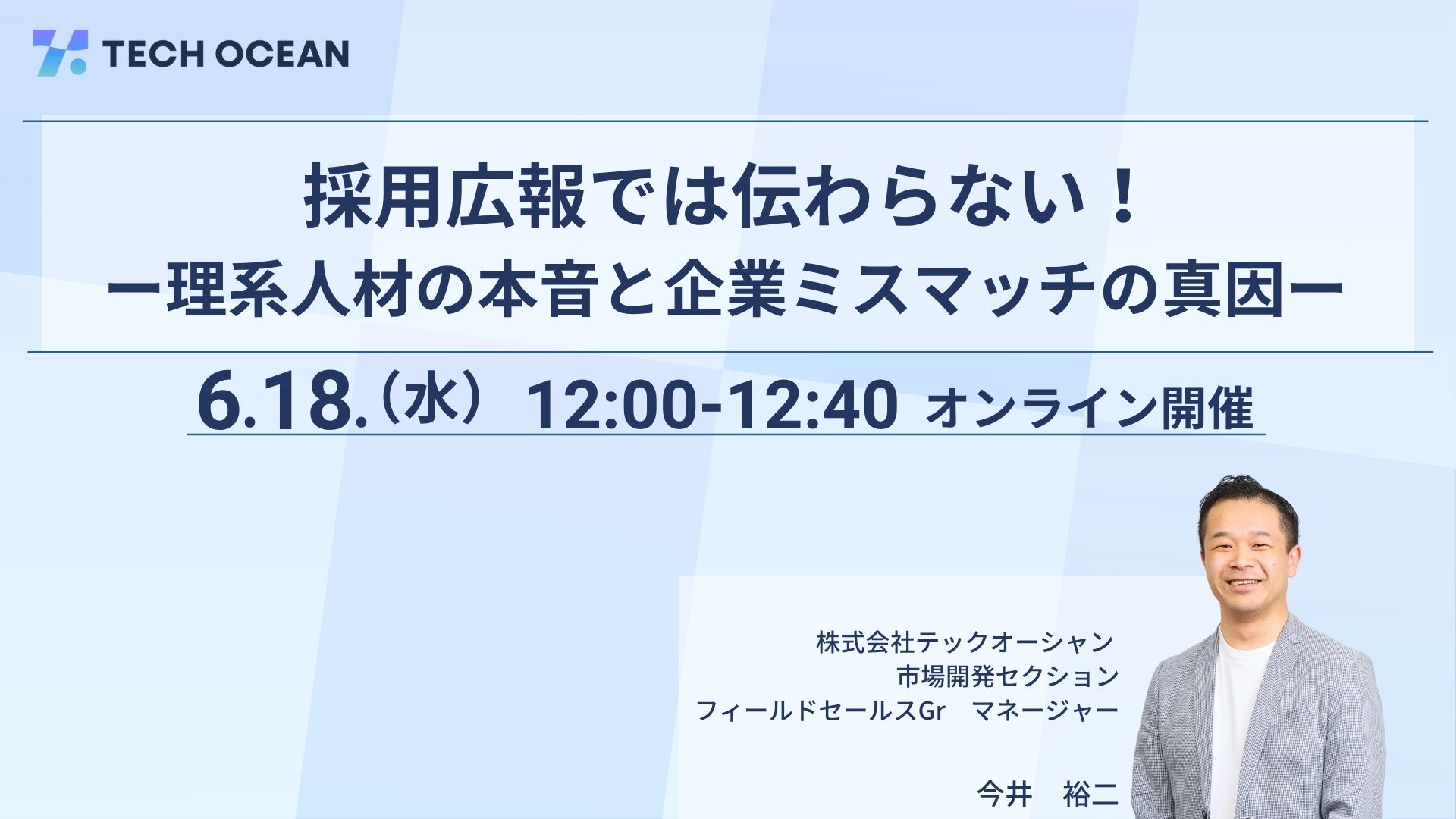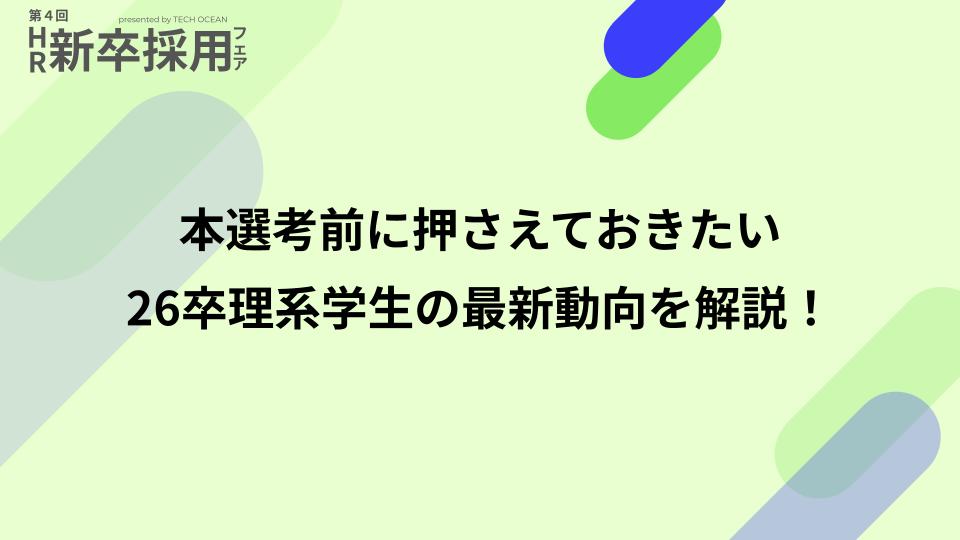Contents
「ダイレクトリクルーティングの進め方を知りたい」
「やってみたけど、イマイチ成果が出ない」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、この採用手法の特徴をよく理解したうえで、ポイントを押さえた対応をすることが欠かせません。
そこで本記事では、ダイレクトリクルーティングで成果を出す方法として進め方やメリット・デメリット、成功のポイントについて解説します。
これから導入を検討している方、導入したけど成果が出ていない方はぜひご覧ください。
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、企業から求職者に直接アプローチする採用手法のことを言います。
従来の「求人広告を出して応募が来るのを待つ」というスタイルに比べて、企業の条件通りの人材に出会える可能性が高いのが特徴で、「攻めの採用」と言われることもあります。
また、以前はダイレクトリクルーティングと言えば、主に特定のスキルを持つ人材の中途採用で使われていましたが、最近は新卒採用でも導入する企業が増えています。
ダイレクトリクルーティングでは、オファー型/スカウト型採用サービス(ツール)を利用するのが一般的です。ただし、広義ではSNSを使った採用やリファラル採用(いわゆる縁故や知人の紹介など)も含まれます。
ダイレクトリクルーティングの進め方
ダイレクトリクルーティングを導入するなら、まずは進め方を知っておきましょう。企業によって違いはありますが、大まかな進め方は以下の通りです。
- 採用計画を立てる
- ペルソナを決める
- 活用するツールを決める
- 魅力的なスカウト文を作成する
- ターゲットへアプローチを開始する
- カジュアル面談をする
- 選考・採用する
Step1.採用計画を立てる
採用活動が成功するかどうかは、計画にかかっていると言っても過言ではありません。
具体的に決める項目としては、採用人数や配属する部署・職種、採用スケジュール、採用活動の予算などがあります。
特にスケジュールについては、年々早期化が進んでいるため注意が必要です。
出遅れてしまうと、後からどれだけ予算や時間をかけても効果が出にくくなってしまうため、計画的に進めましょう。
また、採用基準を社内ですり合わせておくことも大切です。
経営者・採用担当者・現場の責任者など、立場によって求めるものが違うことも珍しくありません。
しっかりと言語化して共有しておきましょう。
Step2.ペルソナを決める
ダイレクトリクルーティングを実施するにあたって最も大切なのがペルソナを決めることです。ペルソナとよく似た言葉に「ターゲット」がありますが、ターゲットは年齢・性別・学部・居住地など、定量的な要素のことを言います。
これに対し、「ペルソナ」はもう一歩踏み込んで、その人の性格や価値観、ライフスタイルなど定性的な要素も想定するのが特徴です。
例えばエンジニア採用であれば「地方国立大の情報学部出身、趣味はプログラミング、新しい技術への興味関心が高い、大手よりも自由な風土のベンチャー企業で自分の力を試したい」のような形です。
このように、ペルソナを聞いた人が「こういう人いるよね」「あの人に似てるな」と想像できるレベルまで解像度を上げておきましょう。
Step3.活用するツールを決める
ペルソナが決まったら、次は活用するツールを決めます。一口にダイレクトリクルーティングと言っても種類は様々です。
一般的にダイレクトリクルーティングではオファー型/スカウト型採用サービス(ツール)の活用が想定されます。
ただし、オファー型/スカウト型採用サービス(ツール)の中でも特徴があります。
例えば以下のような特徴があります。
- ITエンジニア向けサービス
- 理系向けサービス
- 上位大学向けサービス
- 外資系企業向けサービス
これらのサービスそれぞれの特徴を捉え、自社が求める人物像に最もアプローチしやすいものを選ぶことが大切です。
Step4.魅力的なスカウト文を作成する
ツールが決定したら、次は魅力的なスカウト文を作成します。
スカウト文は学生との最初の接点になるため、この文面で興味を持ってもらえなかったら、これ以降のステップに進めないということになります。
募集要項や、ありきたりな紹介文を並べただけでは興味を持ってもらえません。
魅力的なスカウト文については、細かいテクニックがたくさんあるので、下記の記事で詳しく紹介しています。
-640x360.png)
Step5.ターゲットへアプローチを開始する
スカウト文を作成したら、いよいよターゲットへアプローチを開始します。オファー型/スカウト型採用サービス(ツール)なら、登録者がデータベース化されているので、効率的にアプローチすることが可能です。
スカウト文は1通送って終わりではなく、内容やタイミングを変えて2通目を送ってみるのも1つの手です。
開封率や返信率などのデータも参考にしながら、最も効果的なアプローチ方法を探りましょう。
ここまでの内容をより詳しく知りたい方はこちらの資料をご参考にしてください。
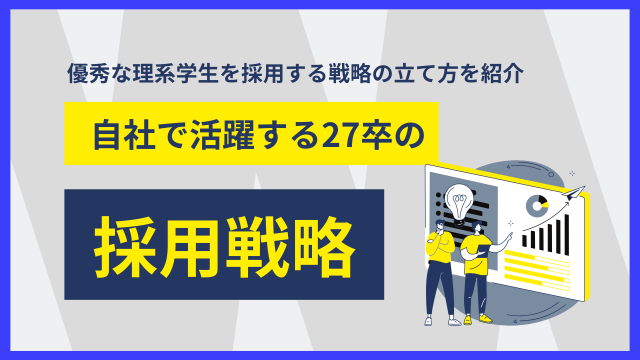
Step6.カジュアル面談をする
アプローチをして興味を持ってもらえたら、次は面談をします。DMやメールを通じて面談の日程をセッティングしましょう。
その際、面接ではなくカジュアル面談とすることで参加しやすい空気を作るのがポイントです。
ほとんどの学生が、この段階ではまだ「どんな企業なのか気になる」程度なので、「志望動機は?」「入社したら何をしたい?」と聞かれても答えられず、困ってしまいます。
まずは緊張をほぐす雑談から始めて、企業紹介や求める人物像などを説明しましょう。
その後、学生の価値観やキャリア志向を引き出す質問をしたり、質問を受け付けたりすると、お互いの理解が深まります。
ただし、学生側の温度感が高かったり、周りの採用選考が進んでいる場合は必ずしも実施する必要はありません。
Step7.選考・採用する
カジュアル面談で応募の意志が固められたら本選考に移ります。必要に応じて、適性テストや複数回の面接などを実施しましょう。
選考では、担当者によって評価がブレることの無いよう、最初に設定した選考基準に従って進めることが大切です。
また、最近は内定辞退の増加も深刻な問題となっています。
内定後に内定者が不安にならないよう、定期的にコミュニケーションをとったり、イベントを開催したりして、しっかりとフォローしましょう。
ダイレクトリクルーティングサービスを活用する場合は、特別感のあるオファーをきっかけに選考・採用に至るケースがほとんどです。
学生にしてみれば、「自分のことを評価してくれそうだ」「大切にしてもらえそうだ」という期待値が高まっている分、選考中や内定後のケアが不十分になると不信感につながりやすいため、注意が必要です。
ダイレクトリクルーティングのメリット・デメリット
ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、他の採用手法と比べたときのメリット・デメリットを理解しておくことも大切です。
それぞれについて、以下で見てみましょう。
ダイレクトリクルーティングのメリット・デメリットについては、以下の記事でもより詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
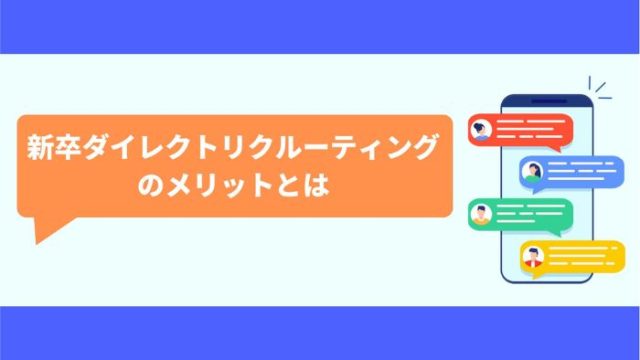
メリット
最も大きなメリットの1つが、自社のことを知らない学生にもアプローチできるという点です。
従来の求人サイトでは、どうしても大手企業や有名企業に注目が集まりがちで、知名度の低い企業の求人は埋もれてしまうことがありました。
その点、ダイレクトリクルーティングなら知名度の低い企業でも「自分にスカウトをくれたのは、どんな企業だろう」と興味を持ってもらえます。
また、母集団の質が向上することもメリットです。
従来のように応募が来るのを待つ手法の場合、集まってくる学生を選ぶことはできません。
しかし、ダイレクトリクルーティングでは自社がアプローチした学生がそのまま母集団となるため、スキルや人物像などは一定の基準を満たした母集団を形成できます。
デメリット
メリットの多いダイレクトリクルーティングですが、最大のデメリットは工数が多く、担当者の負担が大きいという点です。
具体的な業務として、ペルソナ設定やオファー文の作成・送信、個々とのやりとりなどがあります。
特にオファーやスカウトの送信については、時間があるときにまとめて送れば良いというものではなく、毎日コツコツと取り組む必要があります。
また、同時に何百人もの学生と個別のやりとりをすることは難しいため、大量採用をしたい場合には、他の採用手法をとった方が賢明です。
ただし、サービスによっては自動オファーや代行によって工数を削減できるものがあります。
テックオーシャンが提供する理系新卒特化のオファー型採用サービス『TECH OFFER』なら、自動オファーと手厚いサポートによりダイレクトリクルーティングのデメリットを解消できます。

ダイレクトリクルーティングに向いている企業
ダイレクトリクルーティングに向いている企業には、次のような共通点があります。
- 理系の研究職やITエンジニアのように、専門性の高い職種で募集する企業
- 知名度が低く、求人広告だけでは集まりにくい企業
- 有名ではなくても、技術力や独自の価値観を大切にしている企業
- 採用担当者が、スカウトや面談に工数をかけられる企業
採用担当者の工数については、求職者の検索機能が充実しているツールや、自動でスカウト送信できるツールを選ぶことで、ある程度カバーできます。
ダイレクトリクルーティングを成功させるためのポイント
ここからは、ダイレクトリクルーティングを成功させるためのポイントについて解説します。
実は、成功のポイントはたくさんあるのですが、ここでは特に重要な3つに絞って紹介します。
- 採用ターゲットを明確にする
- ターゲットに刺さる魅力を見つける
- 候補者の個別対応を徹底する
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
-640x360.jpg)
採用ターゲットを明確にする
ダイレクトリクルーティングでは、採用ターゲットを明確にすることが重要です。
よく「いい学生が来ない」と言う声を聞きますが、「いい学生」は非常にあいまいな表現です。
例えば、ある企業では「競争心や向上心が強く、アグレッシブな行動をとれる人物」をいい学生と呼び、別の企業では「協調性があり、自分よりも他人のことを優先できるような人物」をいい学生と呼ぶことがあるからです。
同じ「いい学生」という言葉でも、実態としては全く違う性質の人物を指していて、結局どんな学生を採用すれば良いのかがわかりません。
ターゲットを決める際は、なるべく具体的に言語化することで、適切なアプローチができるようになります。
ターゲット設計についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
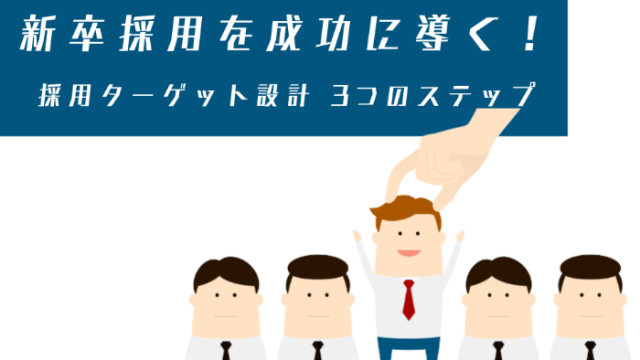
ターゲットに刺さる魅力を見つける
ダイレクトリクルーティングでは、いかにターゲットに魅力に感じてもらえるかが大切です。どのような魅力なら刺さるかを考えなければなりません。
特に中小企業の場合は、大企業には無い魅力を発信することが必要になるため、次のような観点でも自社の強みを洗い出してみましょう。
- 裁量や成長機会
- 意思決定の柔軟性
- 専門性や技術力
- 社会的意義
また、効果的なスカウト文の書き方については、こちらの記事でも解説していますので、ぜひチェックしてください。
-640x360.png)
候補者の個別対応を徹底する
ダイレクトリクルーティングは、採用担当者と学生が1対1でやりとりをする採用方法のため、丁寧な対応が求められます。
中でも注意したいのがメールの内容です。候補者全員にテンプレート通りのメールを送ると、一人ひとりと誠実に向き合っていないと思われてしまいます。
全ての学生に個別対応が難しい場合は、テンプレート対応だと感じさせないよう工夫しましょう。
具体的には、プロフィールを見ないと分からないような、以下の内容を盛り込むことで差別化が図れます。
- どの経歴に魅力を感じたのか
- 入社して欲しい理由
- 入社すればどのようにスキルを活かして活躍できるか
また、個別対応を充実させるためには、なるべく他の部分の工数を削減することも重要です。
『TECH OFFER』のように、オファー送信を自動化できるツールを選ぶのもおすすめです。
ダイレクトリクルーティングを導入して成功した事例2選
ダイレクトリクルーティングは多くの企業に導入されつつあります。攻めの採用として企業側からアプローチするため、欲しい人材を採用しやすいと評価されているためです。
ここからはダイレクトリクルーティングを導入して成功した事例を2選紹介します。ぜひ参考にしてください。
自動オファーによる工数削減で早期採用に対応|イーソル株式会社
イーソル株式会社は、ソフトウェアの開発・製造・販売を手掛ける企業です。
新卒採用ではエンジニアを募集していましたが、理系採用の早期化の波に乗れず、母集団形成に苦労していました。
以前から使っているナビサイトにもスカウト機能はありましたが、採用チームのリソース的に、何千人もの学生に1件ずつスカウトを送信する手間はかけられません。
そこでたどりついたのが、スカウトの一括送信ができる『TECH OFFER』でした。
学生を検索するためのキーワードに「システム」や「ロボット」などを設定することで、自社にマッチする人材をスムーズに見つけられるようになりました。
また、スカウトは一度送って終わりではなく、履歴を追うことで「送りっぱなし」にしないような施策も講じたそうです。
その結果、26卒は現時点(2025年2月)ですでに8名に内定を出すことができ、理系大学院生のエントリーも従来の1.5倍に増えました。
高度なITスキルを持つ人材の獲得に成功|株式会社ラクス
株式会社ラクスは、「楽楽精算」や「楽楽明細」などのクラウドサービスを展開する企業です。
以前はナビサイトへの掲載や合同企業説明会などで、応募が来るのを待つスタイルの採用活動を行っていました。
しかし、この方法では同社が求める「プログラミングの知識+一定のスキルレベルがある学生」という条件にマッチする学生に、なかなか出会えないことが課題でした。
実際に、24卒で入社した13名のうち、ナビサイト経由の人はわずか2名だったそうです。
そこで導入したのが、理系学生の登録者が多く、エントリー数の多さにも定評のある『TECH OFFER』でした。
実際に運用を始めてから3〜4年が経ちましたが、併用している他のスカウトと比べても、『TECH OFFER』の返信率は高い傾向にあると言います。
25卒からは、AIエンジニア、インフラエンジニア、UIデザイナーなど専門性の高い職種での採用も始まりましたが、AIエンジニアは『TECH OFFER』経由で内定承諾を得られました。
ダイレクトリクルーティングを導入するなら理系採用に強い『TECH OFFER』
ダイレクトリクルーティングは、従来の採用手法とは少し違ったステップでの運用が必要です。
特に、ターゲットの設定やスカウト文の作成、カジュアル面談などのステップが特徴的です。
ダイレクトリクルーティングを導入する際は、やみくもにスカウト文を送信するのではなく、送る相手や内容、タイミングなどにもこだわりを持って取り組みましょう。
もし理系学生を採用したいと考えているなら、『TECH OFFER』がオススメです。自動オファー機能を使って効率的に理系学生へアプローチできます。新卒採用で理系学生を採用したいなら、ぜひ1度お気軽にご相談ください。

 が
が