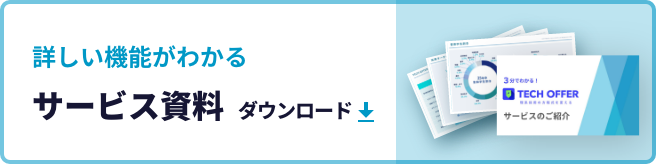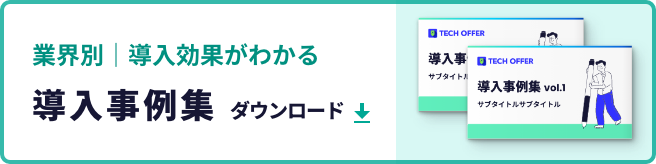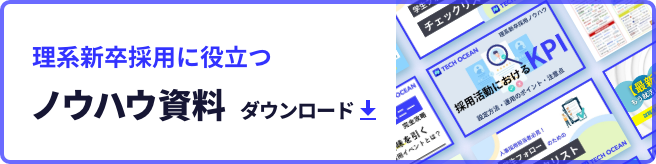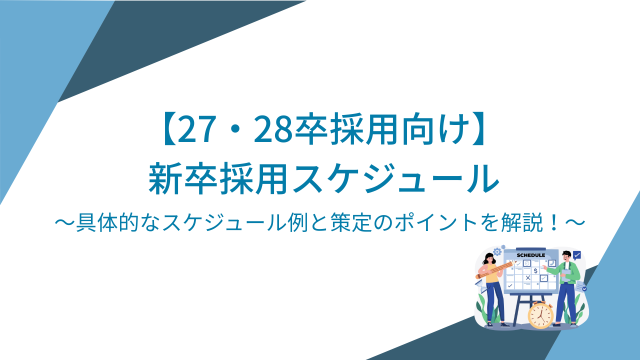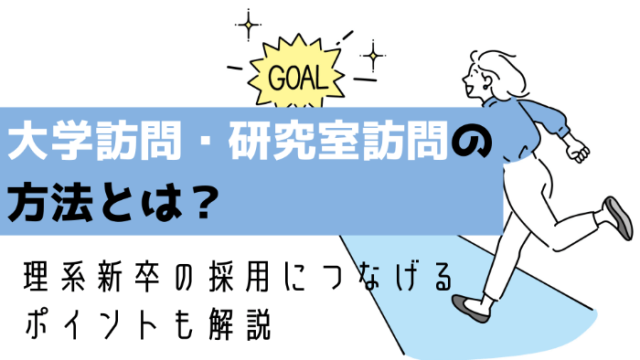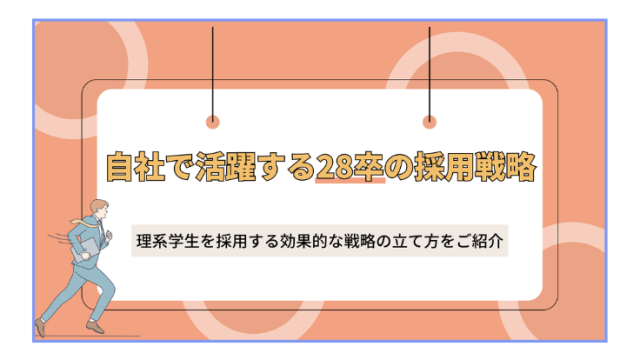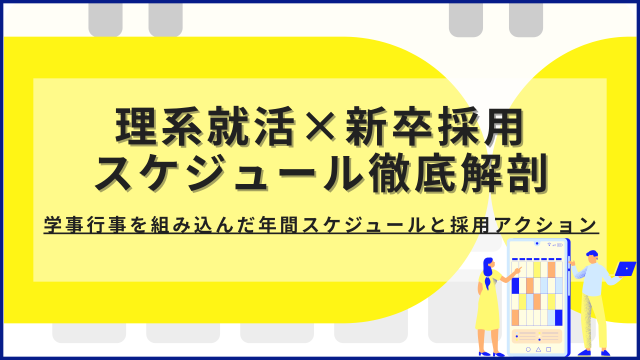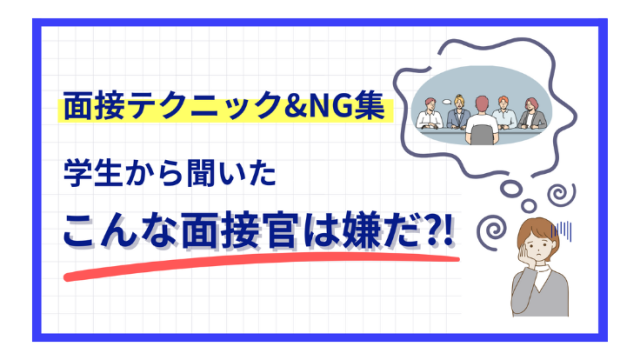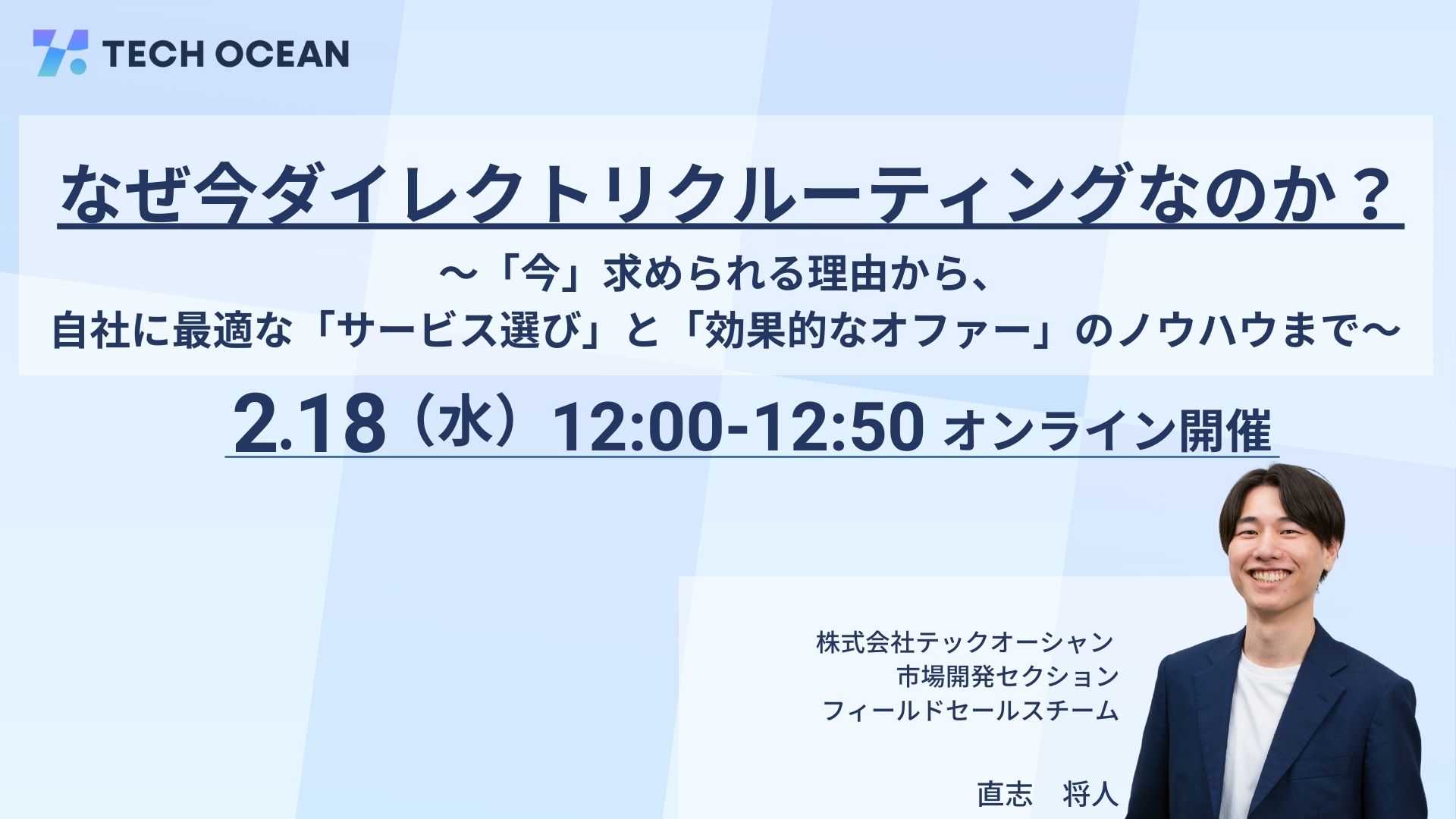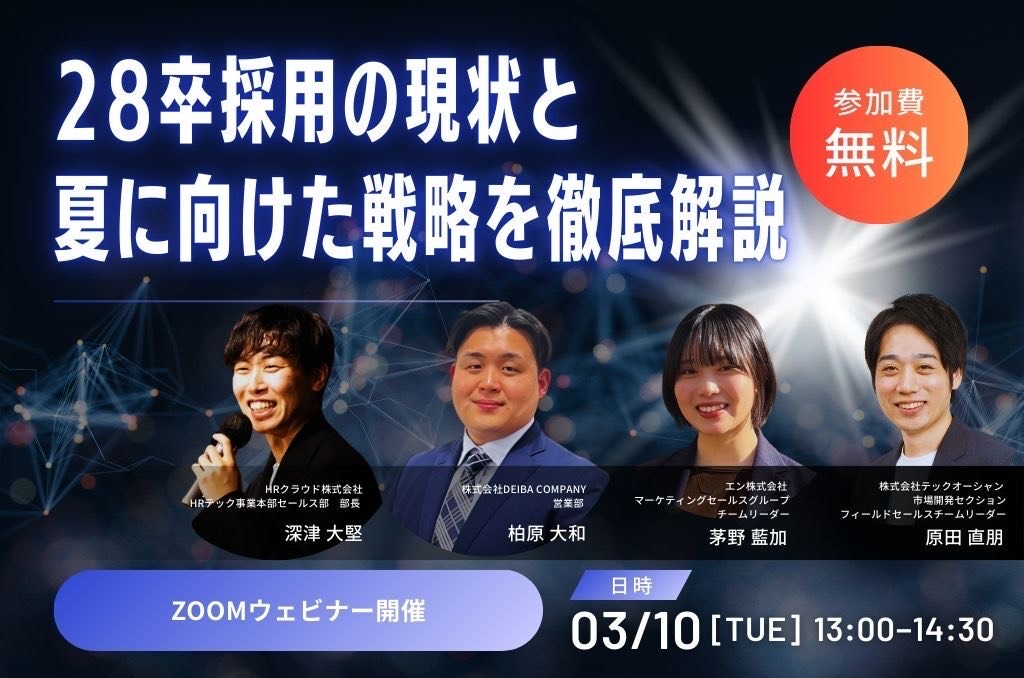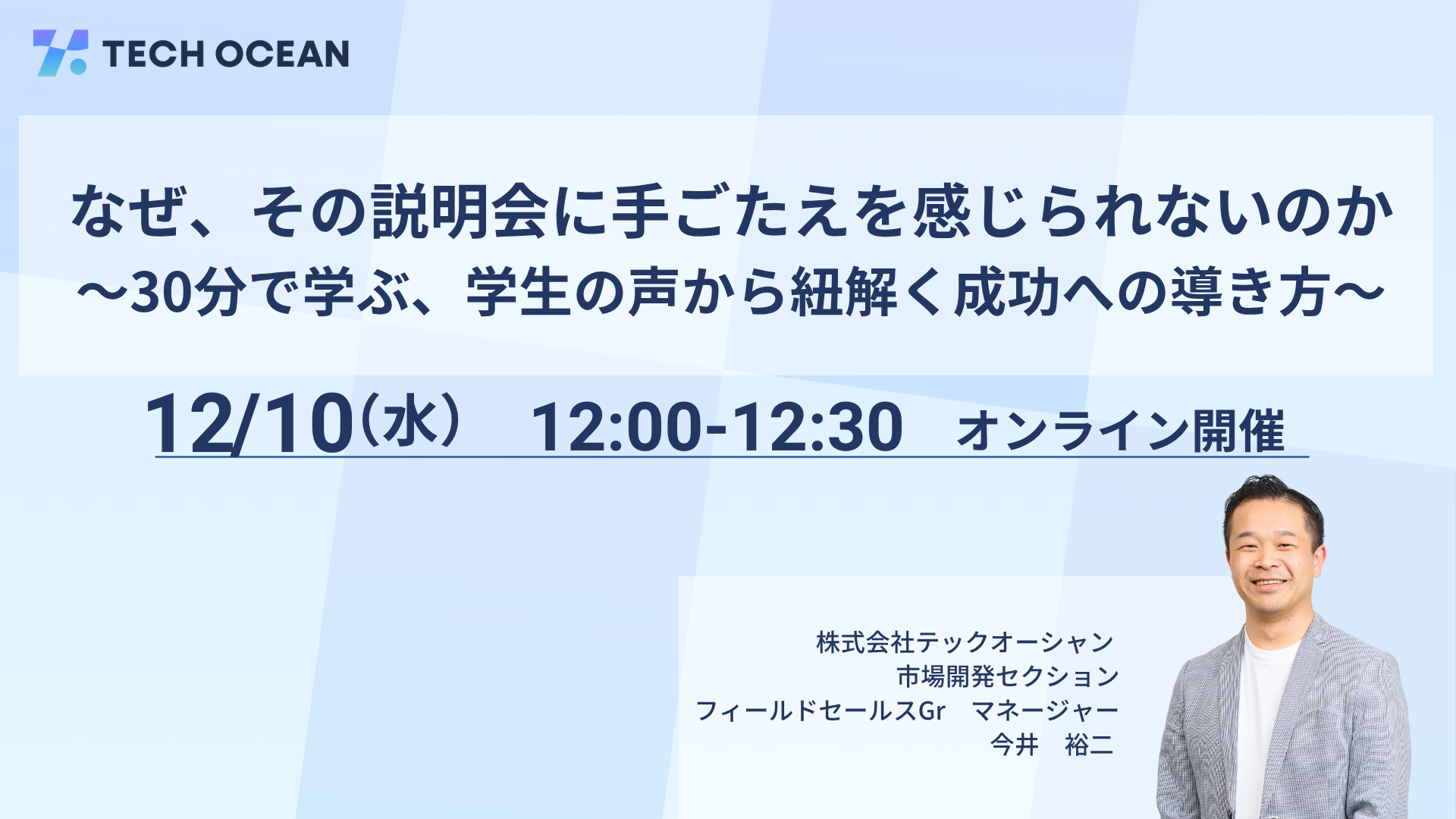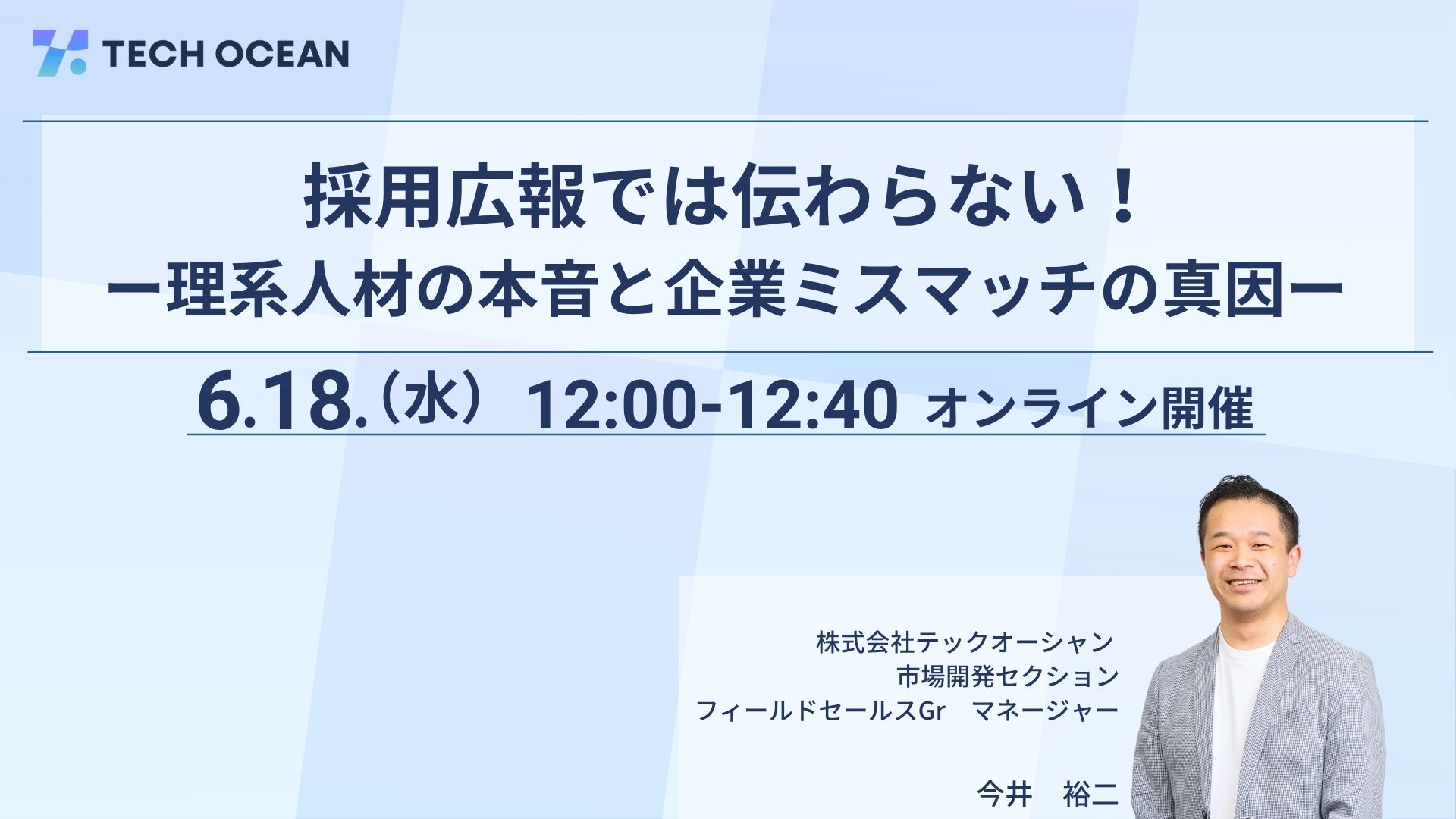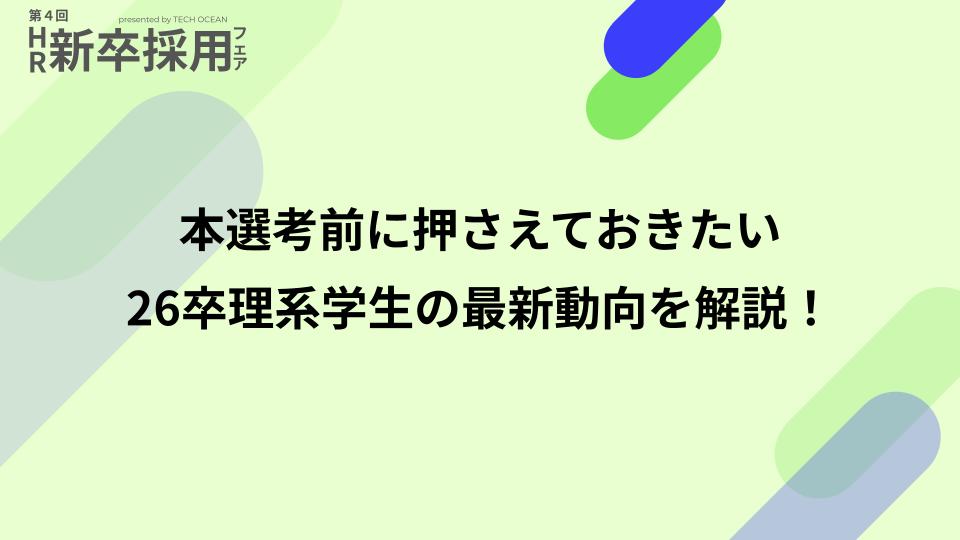Contents
ダイレクトリクルーティングは一般的に中途採用で利用されていた採用手法でした。
近年では採用競争の激化に伴い、近年では新卒採用でも導入されるようになりました。
ダイレクトリクルーティングでは優秀な人材にアプローチできたり、採用活動を効率化できたりとさまざまなメリットがあります。
本記事では、ダイレクトリクルーティングサービス(オファー型採用支援サービス)『TECH OFFER』を展開している株式会社テックオーシャンが、新卒ダイレクトリクルーティングのメリットについて解説します。
新卒採用でお悩みの方はぜひご覧ください。
新卒ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは企業が求職者に直接アプローチする採用手法です。
求職者からの応募を待つのではなく、企業が自社の採用したいターゲットを探し出し、イベントや面談、選考へ直接誘致します。
新卒採用におけるダイレクトリクルーティングとは、採用するターゲットを学生に絞って行います。
具体的には学生のデータベースの中から自社とマッチしている学生を見つけ出し、学生にスカウトメールを送ることで学生と接点を持ちます。
そして、接点を持った学生とやり取りを継続し、関係性を深めていくことで採用につなげます。
新卒採用ではこれまで企業が学生からの応募を待つ「待ちの採用活動」が主流でした。
しかし労働人口の減少による売り手市場などが要因となり、「攻めの採用活動」としてのダイレクトリクルーティングが普及しています。
新卒ダイレクトリクルーティングが注目される背景
新卒採用にダイレクトリクルーティングが求められる背景には、以下のような理由があります。
- 売り手市場による採用難易度の高まり
- 就職活動の早期化
売り手市場による採用難易度の高まり
ダイレクトリクルーティングが注目されている背景の1つとして、採用市場が労働人口の減少による売り手市場となっている点が挙げられます。
少子高齢化などの影響で学生数も減少していることから、新卒採用の難易度も高くなっています。
売り手市場の現代において学生からの応募を待つだけでは十分に母集団を形成することが難しく、こちらから能動的にアプローチをしないと採用に支障が出てしまいます。
そのためサイトや求人サイトのような待ちの採用ではなく、能動的にアプローチができる攻めの採用としてダイレクトリクルーティングが注目されているということです。
就職活動の早期化
早期に就職活動をする学生は情報感度が高いことや意欲的な学生が多いことから、優秀な学生を採用したいと考える企業は採用活動を早期化させています。
この流れに対応するために、ダイレクトリクルーティングが注目されています。
早期から学生にアプローチするメリットとして、優秀な学生と接点を構築できるだけでなく自社にマッチするかどうかを見極める機会を増やせるという点も挙げられます。
採用が難化する中で、せっかく入社した新入社員が早期に離職してしまうことは企業にとって大きな損失となります。
そのような早期離職を増やさないためにも入社前の見極めが重要となっており、早期から学生と関係構築をして自社にマッチするかどうかを見極めることが重要となっています。
その中でダイレクトリクルーティングは、ターゲット学生に絞って早期から接点を持つことができるサービスとして普及しています。
新卒ダイレクトリクルーティングのメリット
中途向けのダイレクトリクルーティングにも共通していますが、新卒においてもダイレクトリクルーティングを活用するメリットは多いです。
ダイレクトリクルーティングを導入するメリットには、以下が考えられます。
- ターゲット学生との接点増加による母集団の質向上
- 自社を知らない・接点がない学生へのアプローチができる
- 自社の魅力を伝えることによる歩留まり率の改善
- 採用ノウハウの蓄積による採用効率向上
それぞれ詳しく見ていきましょう
ターゲット学生との接点増加による母集団の質向上
ダイレクトリクルーティングでは各種サービスのデータベースから学生を検索し、自社の採用要件にあった学生に直接アプローチすることができます。
例えば、大学や学部、スキルや資格、性格や志向性など、自社が求めている学生を詳細に絞り込んで、その中から自社にマッチする学生にアプローチをしていきます。
そのため、ターゲットとなる学生を中心とした質の高い母集団を形成することができます。
自社を知らない・接点がない学生へのアプローチができる
ナビサイトや求人サイトでは、知名度が高い企業や条件が良い企業に注目が集まりやすいです。
また、掲載企業も多く、学生の希望条件に合致していても一覧化した際に埋もれてしまう可能性があります。
ダイレクトリクルーティングでは企業から学生へアプローチするため、学生からの認知がなくても接点を持つことができます。
企業から送るオファー文を工夫することで他社との差別化もしやすく、学生から興味を持ってもらいやすいこともメリットです。
また、学業が忙しく企業を一から探す時間がない学生や、内定を獲得して積極的に就活を行っていない学生に対してもアプローチできるため、ターゲットの土台を広げることもできます。
自社の魅力を伝えることによる歩留まり率の改善
ダイレクトリクルーティングは学生一人ひとりに直接オファーメールを送付します。
メールの内容は自社の魅力だけでなく、入社後の姿や将来のキャリアなど、学生の特徴や就活ニーズに合わせて自社の魅力をアピールすることができます。
個々の学生に寄り添って熱意のあるメッセージを送ることができるため、学生の心に刺さるオファーメールを作成することができます。
そして、オファーメールで学生の志望度を上げることができれば、イベントからのエントリー率の向上や、選考・内定辞退率の低下につなげることができます。
また、入社後のキャリアの解像度を高めることで、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにもつながります。
スカウトメールの書き方について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
-640x360.png)
採用ノウハウの蓄積による採用効率向上
ダイレクトリクルーティングは自社のターゲットとする学生の興味関心や、動向などの採用データを蓄積することができます。
具体的には、メールを通して招待したイベントの内容、メールの文面、待遇、条件などの観点から、反応の良かったメールと反応の悪かったメールを分析することで学生の興味関心や動向を把握します。
ABテストで蓄積した採用データをもとに採用戦略や学生に対しての訴求を見直すことで採用効率を上げることができます。
さらに、年々データを蓄積していくことで、翌年以降の採用活動がブラッシュアップされ再現性のある採用活動を実施することができるようになります。
また、ターゲット学生のみにアプローチできるため、採用要件に合わない学生への対応工数も減らすこともできます。
新卒ダイレクトリクルーティングのデメリット
さまざまなメリットがあるダイレクトリクルーティングですが、デメリットもあります。
ここでは新卒ダイレクトリクルーティングのデメリットを解説します。
- 担当者の業務負担が大きい
- ノウハウやスキルが必要
- 大人数の採用には向かない
具体的な内容について見ていきましょう。
担当者の業務負担が大きい
ダイレクトリクルーティングは他の採用媒体と比べて、採用担当者の業務負担が大きくなる傾向があります。
ターゲットの設定からターゲット学生に合わせたオファー文の作成、学生との個別のやりとりや日程調整、継続的なブラッシュアップなどを既存の業務と並行しておこなう必要があるため工数がかかりやすいです。
ただし、サービスによってはAIによるオファー文作成機能や、条件に合わせた自動オファーの機能があり、ダイレクトリクルーティングの運用工数を削減できるものがあります。
ノウハウやスキルが必要
ダイレクトリクルーティングでは、学生の希望条件や志向性に合わせて訴求方法を変更したり、個々にコミュニケーションを取って関係性を築いたりする必要があります。
場合によってはカジュアル面談を設けたり、特典として選考を免除したりと、新卒採用のカスタマージャーニーを見直すこともあります。
効果的なアプローチスキルやノウハウはすぐに身につくものではないため、中長期的な取り組みが必要です。
ただし、一度ノウハウを構築することができれば採用力の向上に繋がります。
構築したノウハウはダイレクトリクルーティング以外の採用手法でも応用ができるため、自社の採用力向上につながります。
また、これもサービスによっては伴走型支援があるものや採用コンサルティングが付随するものがあり、ノウハウ不足の解消に役立ちます。
大人数の採用には向かない
ダイレクトリクルーティングは学生との密なコミュニケーションが必要となるため、採用人数が多ければ多いほど運用の負担になります。
そのため、ダイレクトリクルーティングは大量採用には向いていない傾向にあります。
ピンポイントで自社にマッチしている学生や獲得が難しい職種での採用を狙うならダイレクトリクルーティングが効果的ですが、大人数の採用を目指すならナビサイトなどの媒体を利用すると良いでしょう。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業
ここまで、ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリットについて紹介しました。
上記の内容を踏まえて、ダイレクトリクルーティングに向いている企業の特徴を解説します。
- 企業イメージの固定化により特定職種の採用が難航している企業
- 認知度が低く、学生との接点が少ない企業
- 継続的な採用を自社リソースで実施できる企業
- 理系学生を採用したい企業
具体的な内容について見ていきましょう。
また、ダイレクトリクルーティングの導入が自社に向いているかをより詳しく知りたい方はこちらの無料ダウンロード資料もご覧ください。
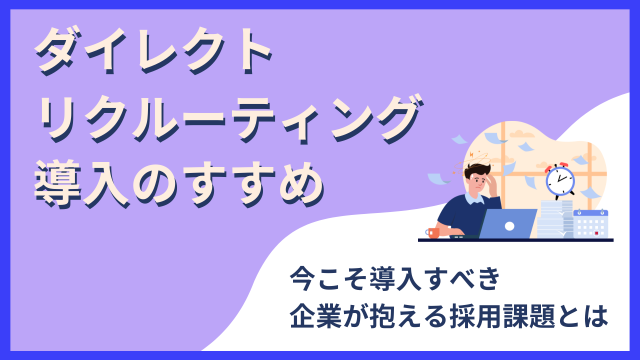
企業イメージの固定化により特定職種の採用が難航している企業
自社のサービスや業界に対するイメージから応募学生に偏りがあるといった課題を抱える企業はダイレクトリクルーティングが向いていると言えます。
例えば、下記のような事例があります。
「営業会社のイメージが強すぎて、特定の分野に精通している専門性の高い学生から興味を持ってもらえない」
「建材、建築メーカーのため建築系の学生は集まりやすいが、システム系の学生は集まりにくい」
「食品メーカーで農学系や化学系の学生はくるが、工場を稼働させるための機電系が来ない」
「金融や保険業界でアプリ開発や新システムの構築でエンジニアが必要になっているのに集まらない」
このような場合、企業が求める職種と学生の企業・業界イメージとで認識がズレていることが多いです。
ダイレクトリクルーティングを利用すれば、自社のイメージに左右されずに学生と接点を持つことができます。
また、学生に対して「自分の能力を活かせる場がある」という新しい発見を提供できるため、興味関心を持ってもらいやすいこともメリットになります。
認知度が低く学生との接点が少ない企業
学生からの認知度が低い企業は学生からの応募を待つ採用媒体では認知度が高い企業に知名度で負けてしまうため、新卒の人材獲得が難しくなります。
しかし、ダイレクトリクルーティングを活用すれば、自社を認知していない学生に積極的にアプローチができます。
認知度が低い企業でも自社の魅力を効果的にアピールすることができるため、応募者を増やすことができます。
継続的な採用を自社リソースで実施できる企業
ダイレクトリクルーティングでは特定のターゲットに能動的にアプローチができるため、採用効率の改善につながるデータを効率よく収集することができます。
具体的には、オファーメールのABテストによって反応率の違いを見たり、イベント参加率やエントリー率の経年変化のデータを蓄積することが挙げられます。
データの蓄積と分析にはある程度のリソースも必要となりますが、それができれば自社にとって最適な採用活動を見つけることができます。
そのため継続的にデータを取得し体系的な採用活動を行っている企業にとっては、ダイレクトリクルーティングは相性が良いと言えるでしょう。
理系学生を採用したい企業
ダイレクトリクルーティングは文理や職種を問わず利用可能なサービスです。
ただし、理系学生を採用したい企業にとっては特におすすめの採用媒体といえます。
理系学生は新卒採用市場において需要が大きいですが、自身の研究活動や学業が忙しいため、認知度の高い企業や採用条件の良い企業に絞って応募をしがちです。
それらの就職活動のタイパ(タイム/パフォーマンス)を求めて、多くの学生がダイレクトリクルーティングを利用しています。
また、理系学生は学業で学んだ自身の専門分野や理系としての素養を活かそうと考える傾向があります。
ダイレクトリクルーティングなら学生が登録する専門分野やスキルから絞り込みを行えるため、学生の意向と自社のニーズに合った理系学生にアプローチを行うことができます。
ターゲットを絞れる企業と理系としての素養を見てもらえる学生のニーズが合致するダイレクトリクルーティングは、企業と学生の双方にとってメリットがあるサービスです。
新卒ダイレクトリクルーティングを成功させるポイント
新卒ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 採用戦略を綿密に立てる
- オファーメールの内容を充実させる
- PDCAを意識する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
また、ダイレクトリクルーティング成功のポイントについてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
-640x360.jpg)
採用戦略を綿密に立てる
ターゲット学生を定めて効率よく採用を行うことが求められるダイレクトリクルーティングでは、綿密な採用戦略を構築することでより大きな成果を発揮することができます。
採用戦略を考えるための要素については以下が挙げられます。
- ターゲット学生の条件、特徴など採用ペルソナの整理
- 学生が入社した後の社内での役割
- 採用活動にかける人員、時間
- 採用目標人数
- 学生へのアプローチの仕方
これらのことを明確にしたうえで計画を立てると、より効果的にダイレクトリクルーティングを活用することができます。
オファーメールの内容を充実させる
学生は「自分に対して興味を持ってくれている」と感じるオファーをもらう企業に対して好感を抱きます。当たり障りのない文面では、他のオファーに埋もれてしまったり興味を持たれなかったりするため効果が期待できません。
また、オファーを送る際に学生のプロフィールを見て、共感した部分や魅力的な部分を示してオファーを送るようにしましょう。
学生に寄り添ったオファーを送ることで学生の志望度が高まります。
PDCAを意識する
より効率的な採用活動を目指すなら、PDCAのサイクルを回すことが欠かせません。
オファーの開封率や承諾率などを分析をすることで、伝わりやすいメッセージ内容や反応の良い学生の特徴を知ることができます。
どのようなメールが効果的で、どのようなイベントに招待すれば学生の反応が良いかを把握するようにしましょう。
PDCAの内容をダイレクトリクルーティングの運用に当てはめると、以下のようなになります。
Plan 採用したい学生像を明確にし、いつどのようなオファーメールを送信するかを決める
Do 学生の心に刺さるオファーメールを作成し、送付する
Check オファーメールの開封率や、承諾率を確認する
オファーメールを開封した学生が自社が採用したい学生とズレていないかを確認する
Action 開封率や返信率の結果から、次回の採用戦略を立てて実行する
まとめ
ダイレクトリクルーティングには次の4つのメリットがあります。
- ターゲット学生との接点増加による母集団の質向上
- 自社を知らない・接点がない学生へのアプローチができる
- 自社の魅力を伝えることによる歩留まり率の改善
- 採用ノウハウの蓄積による採用効率向上
これらのメリットを得るには、しっかりとした採用戦略を立てたり、学生に寄り添ったコミュニケーションなど、丁寧な取り組みが必要です。
また、ダイレクトリクルーティングはメリットだけでなくデメリットも存在するので、自社の適性や現状、採用活動における目標を踏まえたうえでダイレクトリクルーティングを導入するかを決めましょう。
また、導入を検討の方はこちらの事例集もご参照ください。
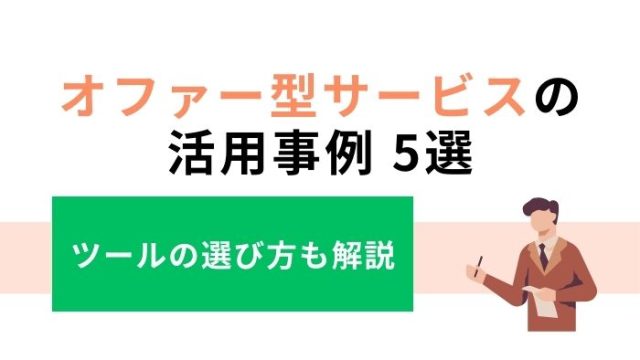
オファー型サービスの活用事例5選
新卒ダイレクトリクルーティングなら『TECH OFFER』
採用活動に割けるリソースが少ない場合、オファー作成や日程調整など工数の多さがネックとなり、ダイレクトリクルーティングの導入を踏みとどまってしまうこともあるのではないでしょうか。
そのような場合におすすめなのが、ダイレクトリクルーティング『TECH OFFER』です。
「キーワードで候補者を選出」「半自動でオファーを送れる」「担当者が設計・運用をサポート」などの特徴があり、工数を削減しながらダイレクトリクルーティングを活用できます。
下記ボタンから『TECH OFFER』のサービス内容がまとまった資料をダウンロードできます。
ダイレクトリクルーティングサービスの導入にお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。
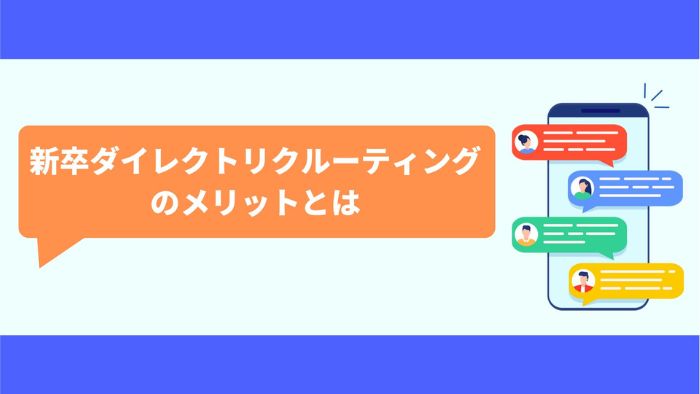
 が
が