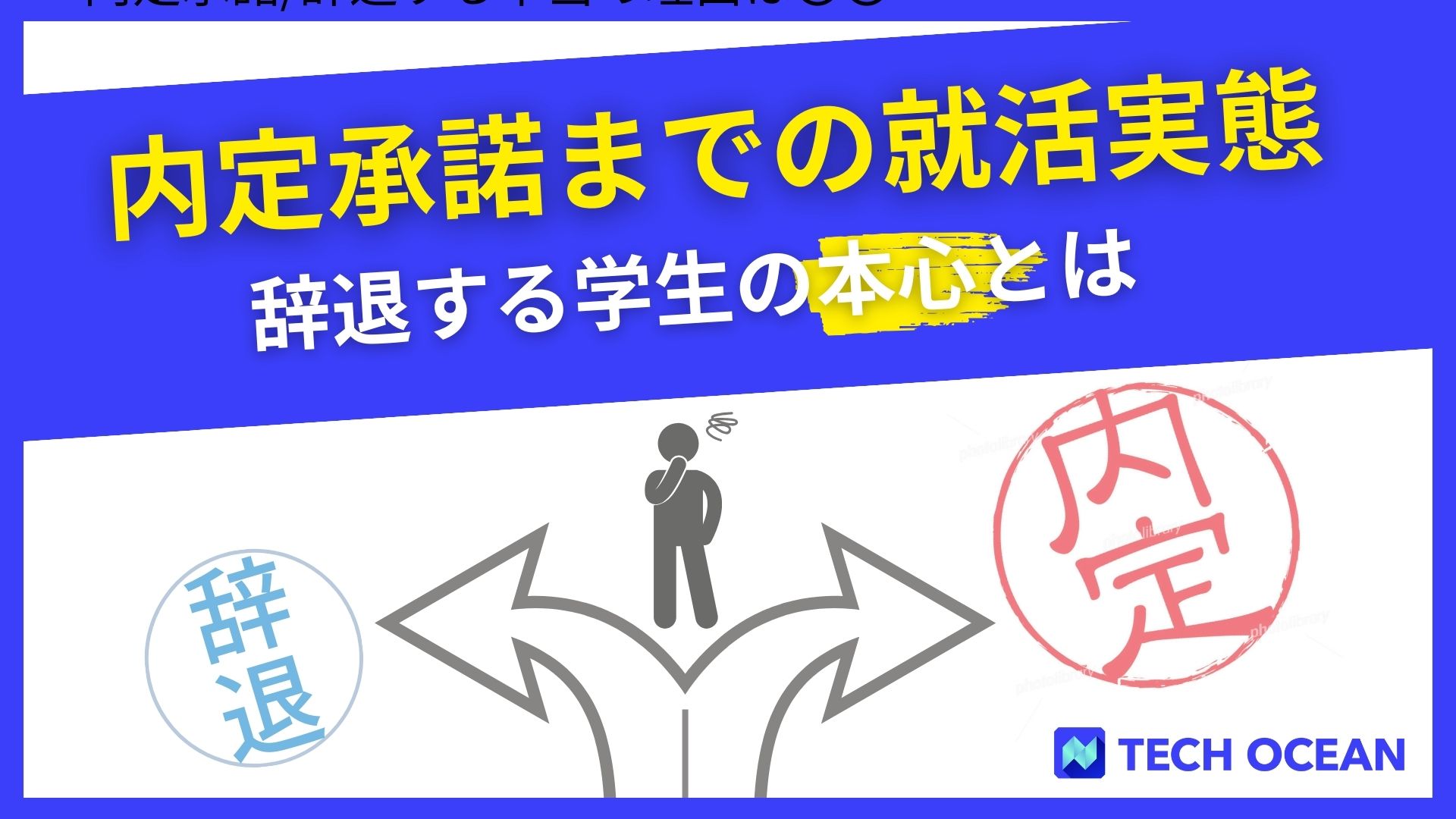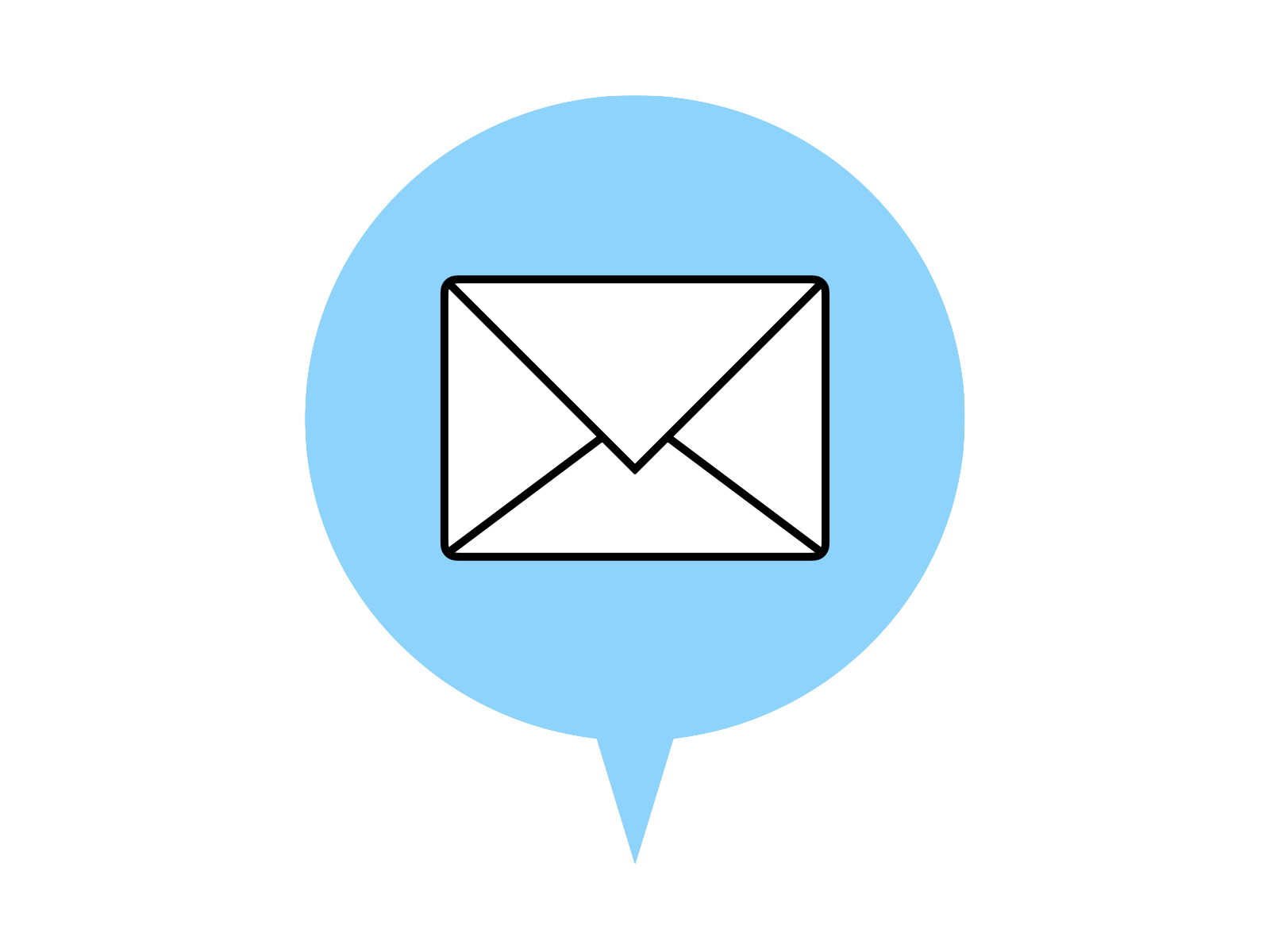– INTERVIEW
理系特化型で母集団形成に成功!自動と手動の良いとこどりで工数削減
業界:通信インフラ、放送、インターネット関連、電力
従業員数:グループ総計16,871名(2022年2月末現在)
-
採用課題
- 理系職種のイメージがなく母集団形成に苦戦
-
導入の決め手/狙い
- 欲しかった理系学生に直接アプローチできる
効果
- ターゲットを絞ったオファーで効率UP 自動オファーで工数も削減
JCOM株式会社
J:COMは「地域の総合サービス事業者」として「お客さまの生活になくてはならないJ:COM」を目指し、札幌・仙台・関東・関西・九州エリアの11社65局を通じてケーブルテレビを始め、インターネット、電話、電力、ガス、ホームIoTとお客さまの心に響くサービスを提供。 さらに、メディア・エンタテインメント事業では、チャンネルの運営、番組の企画制作、映画配給など、メディアとエンタテインメントに関わる、幅広く事業を展開している。
人事部
篤田 明奈 様
取材日:2022/03/04
「理系職種のイメージがない」母集団形成に苦戦

ー21卒採用からTECH OFFERをご利用いただいていますが、それまでの採用に関してどのような課題を持っていましたか?
JCOMでの理系職種の仕事のイメージがつきづらい、ということもあり母集団形成が課題でした。
例えば合同企業説明会などでブース出展をしても、そもそも理系学生の採用をやっていること自体知らない学生も多いので、説明会の段階ですでに集まりづらいというところがありました。そのため、理系学生の人数がもともと多くはないとしても、説明会で中心となるような理系イメージの強い他の会社さんより集まりづらいな、というイメージです。
実際にこのような状況を肌で結構感じてはいますし、実際に何かしらの接点からJCOMの説明を聞きに来てくれた学生に話を聞くと、「あ、こんなに色々やってたんだっていうのを初めて知りました」っていうのをよく聞きます。
ーJCOMというサービスとしての知名度は学生にとっても高いとは思いますが、理系学生の募集と直結するわけではない、というのが難しいですね。
毎年採用人数としても理系が2~3割目標で、2022年であれば130名採用のうち30名程度は理系職種での対応が必要になっているっていうところもありまして、30名採用するための母集団を集めるのが大変なので、昨年はほとんど理系をメインで出させていただいたりとかしてました。
限られた理系人材に対して需要はUP
を知るIS-1024x680.jpg)
ー理系学生採用への意識、理系人材の需要というのが、御社の中でも年々変わってきていますか?
そうですね。
以前よりも採用人数も増やしてきてまして、もともと理系職種の採用を始めたのもここ数年ぐらいからなんです。
一時は10名とかそれぐらいの少ない規模だったのですが、今は高卒含めておよそ30名になっています。実質的な募集人数からみても、結構需要として多いです。
今、中途採用で理系人材が取りづらいっていうところも課題として出てきているので、それであれば新卒の専門知識を勉強している学生、基本的なスキルを身に着けている学生を採用したい、という方針もあり採用人数が増えてきていますね。
ー理系学生が就職して活躍できるのはどのような職種になりますか?
大きく分けると三つの領域があります。
一つ目は、お客様にサービスを提供するためのインフラ設備を運用する領域です。
実際に構築したり企画したり、お客様がサービスを安定して使えるように、監視をするような業務になります。ここが採用のボリュームゾーンで、サービスインフラ領域と呼んでいます。
二つ目は情報システム領域と言いまして、お客様が使うようなシステムとかアプリの開発、社内システムアプリの開発などです。
三つ目は、データサイエンスの領域ですね。完全に理系職種に入れるかはあいまいですが、実際にお客様が使うサービスから得た情報データを分析して、そこから新サービスの提案とかを行うところで、分析の経験がある方に担っていただきたいということもあり、理系学生の採用を行っています。
“理系特化”と“オファー自働化”が課題にマッチ
ーそんな中で、TECH OFFERを導入していただいた決め手はありましたか?
もともと御社のサービスを使う前に、別の会社さんのサービスを使っていたんですね。
そこは理系特化ではなくて、単純にダイレクトリクルーティングができますよというところでやっていたんですけれども、理系学生をターゲットに絞ってダイレクトリクルーティングすることが結構難しかったんです。
理系の母集団がそこまで集められなかったし、そもそも弊社の採用担当の数がそこまで多くない中で回しきれないと言いますか、それほど時間を割くことができない、という状況がありました。
そこで、自動オファーで送れるという点と、理系の学生に特化してオファーできるという点が弊社の課題とマッチしていていいなあ、というところで利用を開始させていただいたという感じです。
ーまさにTECH OFFERの強みを活かしていただいているんですね!具体的にどのように活用していただいていますか?
以前は研究室のキーワードなどかなり絞ってオファーしていたんですが、今で言うと、そこまでターゲットを絞ってるわけではないですね。
募集している3つ領域の中で、サービスインフラ領域が採用のボリュームゾーンになっているところなので、そこに興味がありそうな学生を対象にオファーを出しています。
ーオファーのターゲットとしては広めに設定いただいているイメージですが、採用側の工数としてはいかがですか?
採用側の人数は多くないので、まだまだ手が回っていないところもあります。今年の23卒でいうと、全体での採用人数150〜160名程度を予定していますが、今、採用担当としてはほぼ4人で回しているような状況です。自動オファーも活用して、少しでも工数をかけずに採用できればと思っています。
自動化はオファーだけではない!自動と手動の良いとこどり!
ー実際、TECH OFFER導入前と導入後でどう変わりましたか?
学生が学んでいる領域など、ピンポイントでオファーを送ることができるので、マッチした学生が選考まで進みやすいようになったのかな、と思っています。
特にサービスインフラ領域では、理系の学生であれば分野はどこでも、入社してから学んでもらえるので大丈夫です、という形でとにかく広く募集しないと集まって来ないっていうのがありました。
TECH OFFERを利用させていただいてから、ピンポイントで、本当に欲しい層に送ることができるようになったので、そういった意味での質みたいなところは大きく変わったと思います。
通信の勉強を今までしてたというような知識やスキルがある学生に直接アプローチができるようになったというイメージ、そういった学生に来ていただけるようになったということが、大きいかなと思ってます。
ー篤田さん自身、使ってみた率直な感想としてはいかがですか?
別のダイレクトリクルーティングサービスもと比べて、一番は工数の削減というところですごく助かってるなっていう印象があります。
自動オファーというところはもちろんですが、オファーを承諾した後も「ありがとうございます」というフォローまで自動で送れるなど、設定もいろいろと細かくできるので、そこは非常に助かっているなと思ってました。
他社さんだとオファー承諾のお礼なども自動で送れなかったり、一部の学生に絞ってメッセージを送れなかったりしましたので。
例えば、説明会とかの案内だったら、同じ内容でも大丈夫なタイミングもあるので、そういった面でかなり助かってます。かつ個別にやり取りもできるので、良いとこどりだなと個人的に感じています。
TECH OFFERの担当者との月1ミーティングで最大限活用!
―弊社のコンサルティングサービスについてはいかがですか?
月1回の打ち合わせをして、そこで進捗確認や設定の見直しなどを行っていますが、そこで「この時期なので、この領域を広げよう」とか、細かく見直しをする機会をいただいています。
自分だけでやっていると、「そういう設定もあるんだ」「そうすれば活用できるんだ」っていうところに気づかないで、そのまま運用していることもあると思うので、細かくサポートいただけるのは大変ありがたいなと思っています。
―実際に採用につながった学生の印象はいかがですか?
それまでJCOMのこともなんとなく名前だけ知ってたっていうような学生で、自分からエントリーをしようとしてなかったのに、こちらからオファーして直接接点を持ったことで、すごく志望度が上がったみたいで、結果的に、学校推薦で「御社を第一志望で応募したいです」と言ってきてくれた学生がいたのが、すごく印象的でしたね。
全然興味を持っていなかったところから志望度を高めるきっかけを作れたのは、やっぱりTECH OFFERだったからなのかなと思っているので。
―オファーから日程調整など最大限活用していただきありがとうございます!最後に、採用において大事にしていることを教えてください。
弊社はBtoCの会社なので、部署にもよりますがお客様に近く、お客様と直接関わる社員が多いです。そのため、コミュニケーションを大事にしています。
学生さんにもそれを求めているところがある一方で、面接の中でもコミュニケーションを大切にして、学生さんの話をしっかり聞けるような面接を重視をしています。
学んだ領域以上に、そういった人柄みたいなところを大事にはしていますね。
理系の方だと、こういう領域を学んでいないとダメなのかとか、結構ご質問いただくのですが、スキルが必要なのは一部のみで、大半は理系の基礎知識があれば、全然問題ないんです。
コミュニケーションをしっかりとれる、話すのがうまいとかではなくて、相手の話をしっかり聞いて、それを元に円滑に話ができるっていうところ。そこは大事にするようにしています。
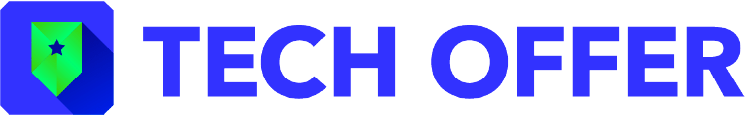


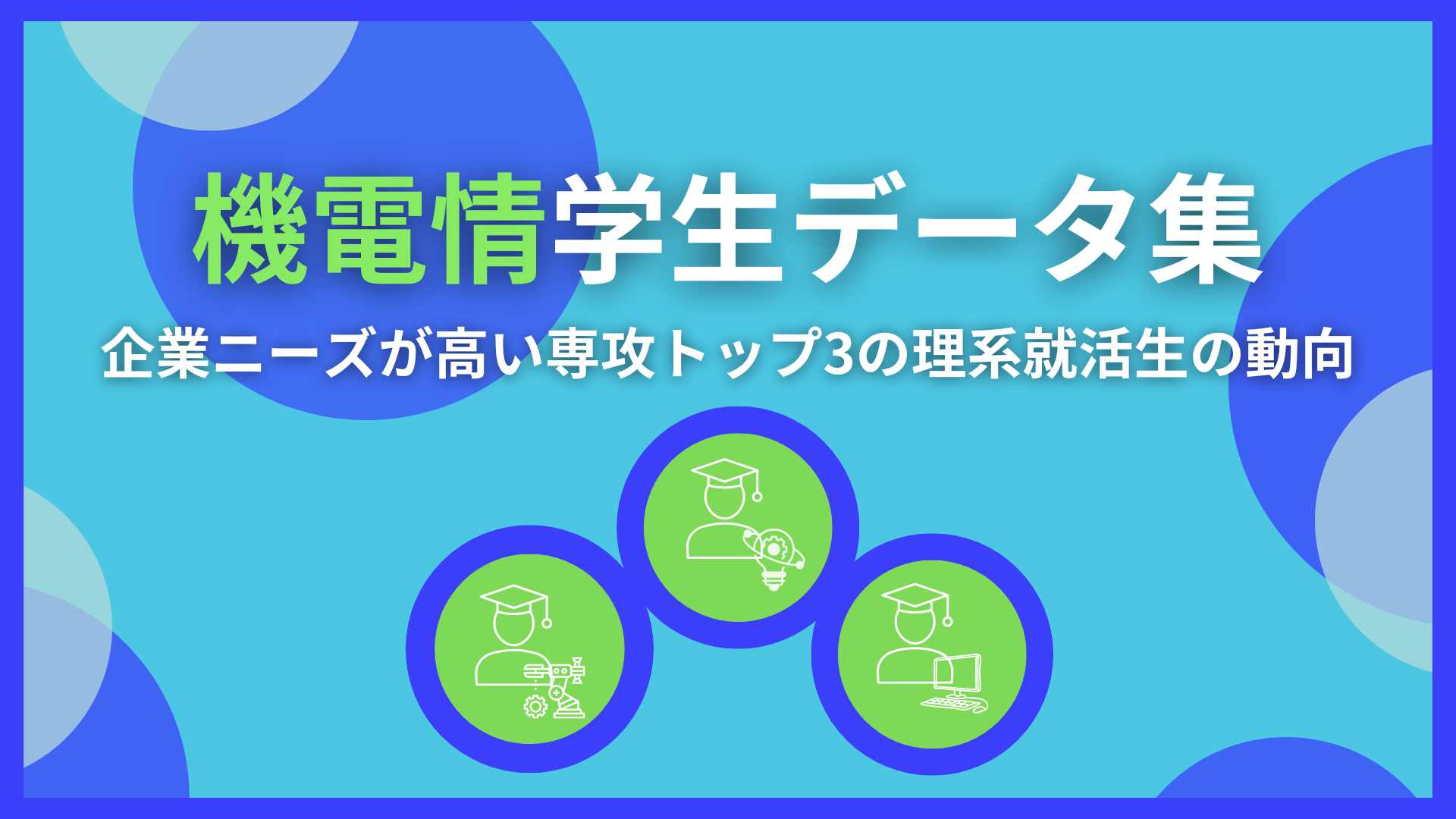
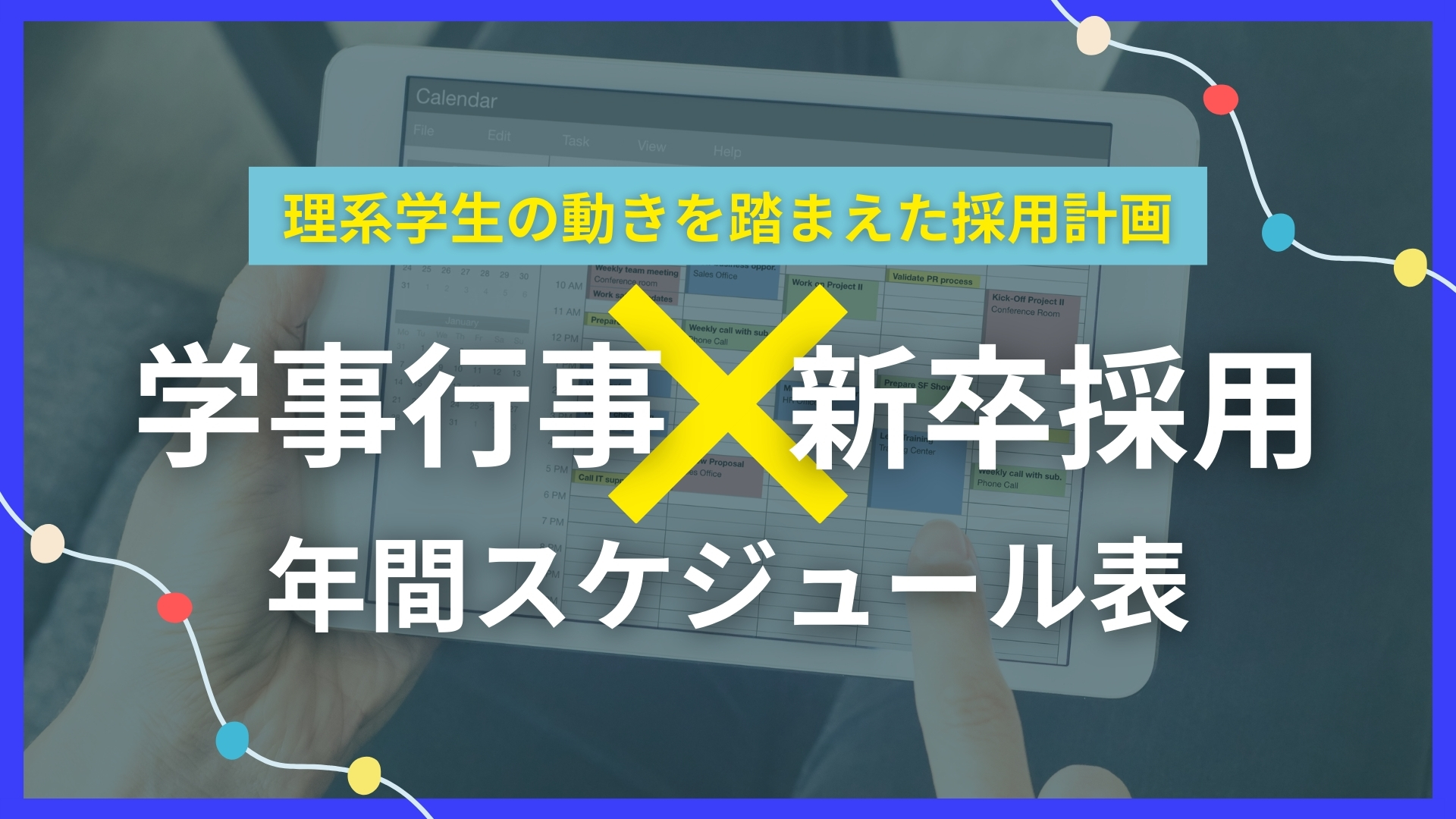
のコピー.jpg)